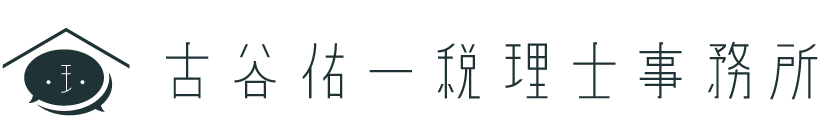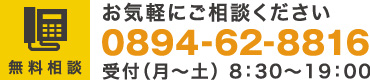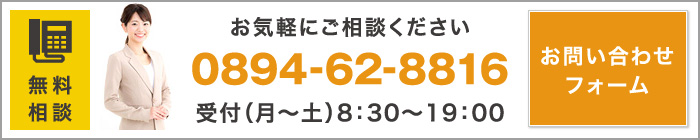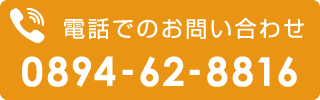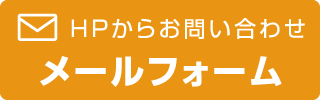こんにちは。愛媛県西予市宇和町卯之町の税理士古谷佑一(ふるやゆういち)です。
今回は、経営者や個人事業主の方にとって非常に有益な制度 「小規模企業共済」 について、税メリットと加入要件を詳しく解説します。
小規模企業共済とは
小規模企業共済は、経営者や個人事業主の「退職金制度」として活用できる国の制度です。
毎月一定額を積み立て、事業を廃業したり退職したときに共済金を受け取る仕組みです。
最大の魅力は 「節税効果」 にあります。
小規模企業共済の大きな税メリット
(1) 掛金が「全額所得控除」
-
毎月の掛金(1,000円〜7万円)は 全額が所得控除 になります。
-
たとえば月額7万円(年額84万円)を拠出すると、その84万円全額が所得から差し引かれるため、課税所得を大幅に圧縮できます。
-
仮に所得税率20%、住民税率10%の方(年収700万円〜900万円)なら、年間約25万円の節税効果が期待できます。
(2) 共済金の受取時も優遇税制
-
受け取るときは、一括受取なら 退職所得扱い、分割受取なら 公的年金控除の対象になります。
-
掛金支払時と受取時の二重で税制優遇されるため、将来の備えと節税対策を同時に実現できます。
(3) 事業承継・廃業時にも安心
-
廃業時には共済金を退職金のように受け取れるため、将来の資金確保策としても有効です。
加入要件 〜誰でも加入できるわけではない〜
ここが非常に重要です。
小規模企業共済は「会社役員なら誰でも加入できる」と誤解されがちですが、加入には厳密な要件があります。
【加入できる人】
- 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
- 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
- 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
- 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
- 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
- 一定の共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
【加入できない人・注意が必要な人】
-
他社に常時勤務するサラリーマンで、副業法人の役員になっている人
-
みなし役員(登記がなくても実質的に経営に関与している場合)
-
使用人兼務役員(役員でありながら従業員としての立場もある場合)
-
常時使用する従業員が21人以上の法人や個人事業主
ポイント
加入可否は 「常時勤務」「主たる収入源」「役員登記」 など複数の要素で判断されます。
「役員だから当然加入できる」と思い込むのは危険です。
よくある加入トラブル例
ケース1
サラリーマンとして別会社でフルタイム勤務しながら、副業で立ち上げた会社の役員になったので加入したい。
→ この場合は 加入できない ケースが多いです。
ケース2
相談役や顧問など実質的に経営に携わる立場であるが、役員登記をしていない「みなし役員」なので加入したい。
→ 税務上は役員とみなされるが、共済では 加入資格なし。
ケース3
法人の使用人兼務役員(役員と従業員の兼務)として加入したい。
→ 主たる立場が従業員と判断されれば、加入できない可能性があります。
まとめ 〜加入要件は要注意!〜
小規模企業共済は、税制面で非常に大きなメリットがある制度です。
しかし、加入要件は意外と複雑で、「役員なら誰でもOK」というわけではありません。
加入を検討する際は、
-
自分が要件を満たすか
-
掛金をいくらに設定するか
-
将来の受け取り方をどうするか
これらをしっかりと確認することが大切です
当事務所では、お客様ごとに最適な加入判断や節税効果のシミュレーションを行っています。
「加入できるかどうか不安」「いくら掛けるべきか知りたい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください(^^)/
税理士 古谷佑一
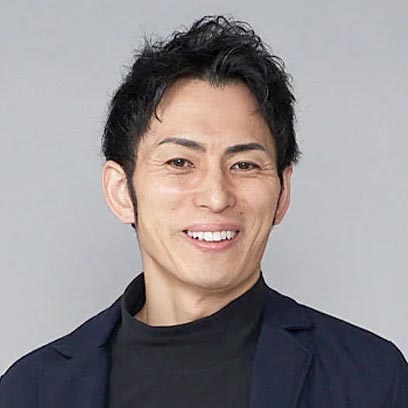
愛媛県西予市を拠点に、松山、宇和島、大洲、八幡浜など県内各地の中小企業や個人事業主の皆さまに寄り添い、税務・会計のサポートを行っています。クラウド会計の導入支援や資金調達のサポート、相続税申告など、幅広いご相談に直接対応し、分かりやすい説明を心がけています。
中小企業経営のサポートを通じて、微力ではありますが地域振興・地域発展に寄与できればいいなというのが私の想いです。
当事務所では、税金や会計、会社設立、相続などに関する不安を気軽にご相談いただけるよう、税務相談についてはGoogleクチコミへの評価投稿を条件に、ご来所・またはzoom等のオンライン相談に限定して無料相談を行っております。
事前予約で365日24時間対応可能。ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。